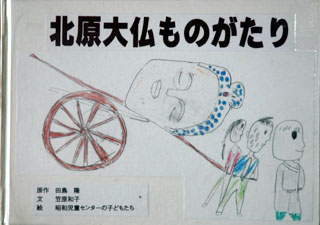|
| 飼っているミツバチの群れが突然消えてしまう 謎の現象が4年ほど前からアメリカで起き始めている。 原因などは謎のままであるが、 その現象を『蜂群崩壊症候群』とよんでいるようだ。 10日ほど前であった。朝日新聞の長野版に 「ハチ足りない・果樹農家悲鳴」 と大見出しの記事をみた。 その記事によると日本のでも三割ほどの養蜂家が 「ミツバチ群が大幅に減ったことがある」 と答えているとある。 原因は、農薬、交配による弱体化などが あげられているが特定はされていないらしい。 ミツバチは果樹・野菜などの花粉媒介に 欠かせない昆虫であるから、農家はたいへんである。 ミツバチに限らず他にも多くの昆虫が 花粉の媒介の役をになっていて、 それらの虫たちが激減しているのは 昨日今日に始まったことではない。 戦後、大量の農薬の使用から 既に始まっていていた。 果樹試験場に研修生で入った頃(1952年)既に、 リンゴ、モモなど花粉媒介の昆虫が少なく 結実が悪く、人間が花粉媒介を している現状を知り驚いた。 既にそんな状態であったから 自然にいるハナバチをふやす方法も 実験的に進められてもいた。 ツツハナバチと云うハチのグループがある。 このグループのハチは細い竹筒、 簾の筒穴などに部屋を作り花粉を集める。 集めた花粉を床に産卵し孵化した幼虫が その花粉団子を食料にしている。 |